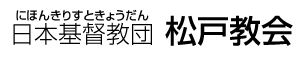ショートメッセージ2012
2012年12月
賢者の贈り物――愛に伴う犠牲
アドヴェント独特の雰囲気によって引き出される事柄や記憶がある。ヘンデルのメサイアを全編とおして聴くことは、十年来アドヴェントの慣例となっている。まとめて二時間半を割くことは難しいが、切れ切れにでも聴きとおさないと何とも落ち着かない。同じように、この時期にふと思い起こすのは、O・ヘンリの短編『賢者の贈り物』である。
貧しい夫婦、ジムとデラは明日にもクリスマスを迎えようとする。しかし互いに贈り物をするための金がない。そこで妻デラは立ち上がる。自分の唯一の宝、シバの女王さえ羨むであろう長く美しい髪を売るために。髪は20ドルに変わり、彼女はそれをもってジムの金時計のチェーンを買い求める。手に取る夫の顔を想像し心高鳴らせながら。
ところが、ジムは帰宅し妻の顔を見るなり重い表情を見せる。デラはその表情に、髪を切ってしまった自分への夫の愛情が消えうせたのではないかと不安を抱く。しかし、夫の差し出した包みを開けた時、デラは涙と共に夫の表情の意味を知る。そこには幾度となく欲しながらも手の届かなった、対の髪飾りが並んでいた。「髪はすぐ伸びるのよ」。デラは感謝を表し、したためていたチェーンの包みを渡す。今度こそ、夫の喜ぶ姿を見られると確信して。けれども、それを受け取ったジムは、ソファに深く座り込み静かに口を開く。「プレゼントは片づけよう。互いに、今すぐ使うには尊すぎる。実は、髪飾りを買うために金時計を売ったのだよ」。「さあ、夕食にしよう」。
この物語がキリスト降誕に際し訪れた東方の賢者の献げ物を土台にしていると知ったのは、これを初めて読んだ中学時代から遠く離れてからであったが、そう思って読み返すと、クリスマスに贈るプレゼント、あるいは神への献げ物について大切なことを問われているような気がする。
著者は、最も大切なものを犠牲にして互いの愛を表現したジムとデラ、この一組の男女にまことの賢者の姿があることを語るのだろう。
読者はおのずと、自らがいかにこの賢者に続く者となりうるかとの問いへと招かれる。
「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」
(ヨハネによる福音書3章16節)
主イエス・キリストを送り遣わしてくださった神の愛に、何をもって応えよう。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年11月
教会の教育――子の前に立つ信仰
「答え」のないものの一つに教育がある。これぞ正解と胸を張って子に向かうも、ものの見事に砕かれた個人的事例は枚挙にいとまがない。子のことで何も悩みがない人は贅沢税を払うべきだという笑い話を聞いたことがあるが、うまく笑えなかった。そのような税はいつまでも納められそうにない。
その中でも一つ慰められるのは、子の前に立つのは親だけではないということである。親族の交わりがあり、地域社会の交わりがあり、何より教会の交わりがある。親の責任を軽視するつもりはないが、事実、我が子は我が子であり、同時に教会の子である。そう思うと少し肩の力が抜ける気がする。
四、五歳の幼児にはいわゆる宗教的な思考の枠組みはないといわれる。彼らにとっては来るべき神の国を語る黙示文学も、「むかしむかし」と語り出される童話も、天使も人形も同じ地平に存在する。しかしやがて彼らが神の名のもとに抱く観念があるとすれば、それは大方この年頃を過ごした人間関係で決まるという。神の愛に安らぎを見るのか、神の厳しさに怖れ身を縮こまらせるのか、あるいは神に対して無関心を装うか。それは彼らの幼少期に彼らの前に立った、両親をはじめとする人々、その人々の信仰に依るところが大きい。子の前に立つ人間存在が問われている。
教会教育とは何か。思いめぐらし試行錯誤している。「結論的に言うと、宗教教育の目的は子どもに聖句を暗唱させたり聖書の話を覚えさせたりすることではない。こんなことは副次的なものにすぎない。肝心なのは、子どもを愛する能力をもつ人間、他人のために献身できる人間に育てることだ」。
教会教育(宗教教育)の目的を語る旧西ドイツの牧師イエル・ツィンクの言葉は、言葉としてはわかる。ところが、どうすればこの目的に辿り着けるのかがわからない。否、「どうすれば」などと問うている時点で、すでに手っ取り早い小手先の技法を求めていて、人間存在そのものを問うことを疎かにしているのだろう。「答え」はない。それでも幼児祝福式を前に、教会の子どもたちの前に立つ自らの信仰を問うてみる。
「心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず/常に主を覚えてあなたの道を歩け」(箴言3章5-6節)。
主に信頼する者として子どもたちの前に立ちたい。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年10月
教会と死者――天上の礼拝に連なる教会
時折、教会は死者に関心を寄せていないとの声を聞く。それは全く当てはまらないと、即、弁明したいところだが、実際にそういう見方があるとすればひとまず甘受する。
過日、東日本大震災の被災者のひとりである僧侶のお話しをうかがった。自ら寺を失う経験をされながらも、犠牲者とその家族のために力を尽くされる姿に多くを教えられた。加えて、その席で立った質問者の問いに考えさせられた。質問者は問うた。あの惨事に際してねんごろな供養がかなわなかったために死者の霊を目撃する人が多いと聞くが、これをどう考えるかと。車で人をひいてしまったと警察に駆け込むも、被害者の見当たらない事例があるのだという。この問いには、被災者は皆疲労困憊しているとだけ回答があった。
教会は死者を送る。ただ、残された者の送る行為自体が死者の天に帰るか否かを左右するとは考えない。死者に関心を寄せていないのではない。それはひとえに死者を迎える神を信頼してのことである。「生きるにしても、死ぬにしても、わたしたちは主のものです」(ローマの信徒への手紙14章8節)。我々は主のものであるゆえに、主に委ねる幸いを知っている。生きるにしても、死ぬにしても。教会にはすべてを神に委ねる信仰が与えられている。
永眠者記念日を迎える。我々は死者を偲ぶために、礼拝堂に集い、墓前に集う。教会も死者を大切に思う。しかし、その思い方は、死者の平安のために何かをなすという仕方ではなく、死者をもご自分のものとしてくださる神を礼拝するという仕方で表される。それゆえ、教会は死者を思うとき、いよいよ神を賛美する。
教会にはいわゆる初七日、四十九日の法要にあたるものはない。だからといって、教会が死者に関心がないというのは当たらない。ただ、先の声が教会に向けられることに、我々はもっと自覚をもたなければならないのではないか。それを無理解の一言で片づけることはできまい。
教会こそ死者を常に思う群れである。特定の日に限らず、元来、主の日の礼拝をささげるということは、天上の礼拝に連なる行為である。礼拝において教会は天上の礼拝の前味を味わっている、と教えてくださった師の言葉を思い出す。そうだ、教会は先に天に帰られた先達の礼拝、天上の賛美を思いながら、今、地上で主を礼拝するのだ。
主の日ごとに天上の礼拝にある平安と喜びを味わいたい。天上の礼拝者を思いつつ。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年9月
託された主の教会――ひたすらに主の霊を求めて
バビロニアでの五十年に及ぶ捕囚生活から解き放たれた神の民イスラエル。彼らの喜び帰った郷土は荒廃の限りを尽くしていた。エルサレムの神殿も、町並みも、ことごとく崩壊し瓦礫の山となっている。
途方に暮れる人々の間に、神から遣わされた預言者ゼカリヤ。ゼカリヤはどの家よりも先に神殿の再建を訴えた。自分たちの住む場所もままならないところで神殿の再建とは。懸命の訴えに人々は重い腰を上げるが、眼前の瓦礫がその心を萎えさせる。更地からの再建ではない。
その中でゼカリヤは幻を見た。金の燭台に、七つの管があり、七つのともし火皿が付いている。「主よ、これは何でしょうか」。ゼカリヤの問いに御使いは答える。「その七つのものは、地上をくまなく見回る主の御目である」。幻は、再建作業に虚しさをおぼえるイスラエルに、くまなく主のまなざしが注がれていると伝える。さらに燭台の左右に二本のオリーブの木が立つ。「燭台の右と左にある、これら二本のオリーブの木は何ですか」。「これは全地の主の御前に立つ、二人の油注がれた人たちである」。幻は、神により選ばれた二人の人、政治家ゼルバベルと大祭司ヨシュアにイスラエルの再建が託されると告げる。
ただ、二人は彼らの才覚のみにより再建を果たすのではない。「武力によらず、権力によらず/ただわが霊によって、と万軍の主は言われる」。祖国復興は二人の英雄の力によるのではなく、ただひたすら主の霊、その力によって成し遂げられる。(ゼカリヤ書4章)
本年10月1日をもって松戸教会の歩みは109年の年月を数える。古今東西、教会の歩みはそうであるが、教会には順風の日もあれば、逆風の日もある。折々に取り除くべき瓦礫が散在する。その中で、この群れはキリストの体として立ちつづけてきた。その歩みには多くの先達の献身がある。喜びがあり、涙があり、祈りがある。そのことを忘れてはならない。そしてそのさらに背後には、主の霊による導きがある。このことを決して忘れてはならない。
9月30日、教会懇談会を開催する。今、我々に託された主の教会をいかに保ち、次の世代に受け渡すのか。与えられた知恵を尽くして協議したい。取り除くべき瓦礫を数えれば一つや二つではない。しかし、我々は瓦礫に心萎えさせることなく、主の霊による導きがこの群れに伸べられることを信じ、ひたすらに主の霊を祈り求める群れでありたい。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年8月
歴史を愛する――神に立ち返るとき
「ぜったいに外に出られないってこと、これがどれだけ息苦しいものか、とても言葉には言いあらわせません。でも反面、見つかって、銃殺されるというのも、やはりとても恐ろしい。こういう見通しがあまりうれしいものじゃないのはもちろんのことです。」アンネ・フランク・ハウス編『未来へ向けての歴史の叫び アンネ・フランク』
自分の書いた日記が世界中で読まれ、第二次世界大戦中にユダヤ民族が受けた険しい迫害を後世に語り継ぐことになるとは、当時13歳の少女、アンネ・フランク自身、想像だにしなかった。ナチス占領下のオランダで家族と近しい人々と身を寄せ合う生活の記録は、2年以上に及んだ潜伏生活の苛酷さを物語っている。隠れること自体に伴う息苦しさ、いつだれに見つかるかもしれない恐怖、心を休める暇のない緊張・・・。そこには声に出すことさえ許されなかった少女の叫びが書き刻まれている。
一方、緊迫した状況下、我が身を危険にさらしながら一家を支える一握りの協力者がいた。日記には、アンネが協力者ミープに寄せた信頼と、彼女から受け取った光が描かれている。
「ミープはまるで荷駄を運ぶラバみたいに、忙しく使い走りをしてくれます。ほとんど毎日のように、わたしたちのために野菜を手に入れては、いっさい合財を買い物袋に詰めこみ、自転車で運んできます。土曜日には、図書館から本を借りてきてくれるので、みんなはその日を待ち焦がれています。まるでプレゼントをもらう小さな子供みたい。」
アンネは本を愛し、歴史を愛した。「大嫌いなのは、代数と幾何、そして計算。これ以外の学科は何でも好きですが、なかでも歴史がいちばん好きです。」アンネの愛した歴史とはいかなる歴史か。それはユダヤの民の歴史、神の民イスラエルの歴史である。それは神への従順と背反の繰り返しの歴史であり、時に目も当てられない罪を覗かせる歴史である。けれどもアンネはそれを愛した。それは、彼女が歴史の中に悔い改める者の立ち帰りを待ち、赦す神を見ていたからではないか。それゆえアンネはまた歴史に希望を見ることができたのではないか。
「この日光、この雲のない青空があり、生きてこれをながめることのできる限り、わたしは不幸ではない。」
神を見失った歴史の悲惨と向き合う季節。歴史に伸べられる神の御手を見出し、悔い改めをもって神に立ち帰り、光を見出す、そのような季節としたい。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年7月
声をそろえて―共に招かれた群れとして
賛美の集いが開催された。教会オルガニスト、その指導を受けている練習生、そして教会聖歌隊により、音色と歌声をもって主が賛美された。音楽をとおして一同がひとつ主に思いを馳せるよきときとなった。このために多くの祈りと備えが重ねられてきたことを知る者の一人として、演奏者に主のねぎらいが豊かであることを祈る。
音楽について何かを語る資格を持ち合わせていないが、いつも思うのは声をそろえて歌うことの難しさと、それを得たときの喜びである。
時折、讃美歌自動伴奏器を用いて賛美することがある。寸分たがわず音程を示し、リズムを刻んでくれる伴奏器は、たとえば楽器のない場所で賛美するとときに大いに力を発揮する。ところが、これに合わせて歌うには、相当の訓練を要する。伴奏器は「正確に」拍子を打つのだが、歌う者の声はその前に行ったり、後ろに行ったりで、「アーメン」と曲を閉じて何とか帳尻を合わせることもある。
転じて、奏楽者に導かれる賛美でそのようなもどかしさを感じることはない。会衆と奏楽者、会衆と会衆の息が一体となる。自動伴奏器の経験からして、それは奏楽者の砕く心によるところが大きいのではないかと想像する。
弦楽の奏者と声楽の歌手が協演することについて聞いたのは、息を合わせる大切さである。弦楽の奏者はその技術によって、弓を返すときでも一定の音を出し続けることができる。ところが、歌手には肺活量による制限がある。その両者が息を合わせるために、奏者は歌手のブレスを意識するとのこと。
礼拝において声をそろえて賛美することを教会は大切にしてきた。ある人は、礼拝では斉唱(単律で歌うこと)こそ望ましいという。神の御前で一つ共同体として歌うということを突き詰めると、そういう結論に至るのかもしれない。一方、礼拝者には斉唱か重唱かという形式の問題にとどまらず、隣人と共に神の前に立つこと自体が問われているのだろう。賛美に限らず、礼拝では詩編交読や信仰告白、そして主の祈りと、共同の賛美や祈りがささげられる。独りではなく、共に神の前に招かれた群れとして、心を通わせ、ささげうる最上の賛美と祈りを主にささげたい。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年6月
かの地に立ち 忘れることは決してない
過日、東日本大震災による被災地を訪れる機会を得た。仙台から沿岸部に向かい仙台平野より松島、石巻、南三陸、気仙沼へと北上した。およそ500㎞に及ぶといわれる津波被害地域からすると、その一部を通ったに過ぎないが、車窓からでさえも事柄の重さが感じられた。そして昨年5月、やはり同地に立ったときのことが思い出された。そこには鉄骨のみを残した建造物、散在した家財をむき出しにした家屋、根元で折れ曲がった電柱、建物の屋根に打ちあげられた舟があり、土埃が立ち上がっていた。視覚的な記憶だけではない。そこに漂っていた何ともいえぬ臭気が鼻の奥で再現された。
一方、傷跡を残しつつも、一年と3ヶ月を経た同地には変化も見られた。仮設住宅が建ち並び、復興市場なる商店街が出現していた。外面だけのことではない。精神衛生や福祉の分野においても各方面から力が注がれている。その中でキリスト教会の果たす役割は小さくない。昨年末には地域の要請によりクリスマス会が開かれたとのこと。「キリストさんはええ。」土地柄からして決して聞かれることのなかった声が所どころで聞かれるという。傷ついた人々に寄り添い続けるキリスト者の姿を想像する。
一人の奉仕者に被災された方が胸の内を語られたという。「支援はありがたい。でもいつか忘れられるのが怖い。」支援の輪が広がれば広がるほど、やがて忘れられるかもしれないという思いが心に迫るのだろう。その心の内は、わたしには想像さえできない。
「女が自分の乳飲み子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ、女たちが忘れようとも/わたしがあなたを忘れることは決してない。見よ、わたしはあなたを/わたしの手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常にわたしの前にある。」(イザヤ書49章15-16節)
我々の意思は弱く、心もとなく、「決して一時も忘れない」といえる者はいないだろう。しかし、唯一、我々をお忘れになることのない方がおられる。その方のまなざしが今もなお、かの地に住まう人々に向けられている。この確信を語るべく人々に寄り添う奉仕者の働きにこれからも連なりたい。
海辺にはかすかに潮の香りがした。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年5月
あなたの日曜日 まことの安息を求めて
ここ数週にわたり、ヴァルター・リューティの著した『あなたの日曜日』からの引用文を教会前、掲示板に掲載している。1949年に出版された書物でありながら、そこには現在の社会状況、あるいは広く教会の状況を見越したかのような言葉が綴られている。文章の軽快さに似合わず、重い警告と読んでいる。次のような一節がある。
「毎週24時間の休息!これが7年重なれば、1年分の日曜日の休息を得ることになります。そして70年たてば、10年分の日曜日を回想することができます。人生全体で考えるとかなりの量になるこの時間を、それが設けられた目的にかなって過ごすか過ごさないかは、決してどうでもいいようなことではありません。あれやこれやで過ごした十年は、それなりに人間のからだに痕跡を残しますし、また、人間の魂にも痕跡を刻まずにはいません。」
ヴァルター・リューティ『あなたの日曜日』宍戸達訳 新教出版社
終始、休息の必要性を訴えるこの書物から多くのことを教えられる。人には単なる休日ではなく、まことの安息が必要だということ。そしてもしそれを失っているとすれば、人は回復するのに多くの時間と労力を要する“痕跡”を刻んでしまうということを。
これを読みながら現在の社会的、教会的状況を見渡すと、労働にしても、学業にしても、家事にしても、奉仕にしても、おおよそ人の営みに活力や喜びがないとするならば、それはまことの安息の欠如に端を発する問題だと思わされる。
“主日礼拝厳守”は、日本の教会が大切にしてきた尊い伝統である。しかしそれが言葉面としてだけ受け継がれるとき、形骸化することもある。問題は日曜日に教会に行くこと自体ではない。問題は日曜日、教会において、礼拝においてまことの安息に与(あずか)ることだ。そこで生けるキリストに出会い、そこで命の息を吹き込まれて生きることだ。それが創造の秩序にかなった安息を知ることの内容であり、“主日礼拝厳守”のこころである。
人をまことに生きる者とする命の息、聖霊を待ち望む期節、聖霊降臨日が近づく。まことの安息の必要を知る人々に、否、おぼろげにでもその必要を思い始めている人々に、教会がそれを供することができているのか。自らに問うている。
まことの安息に生きる教会が建てられますように。そこに人が集い、神との間にまことの憩いを得ることができますように。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年4月
十字架と復活 なおも光に生きる
棕櫚の枝をかざし「ホサナ」と主イエスを迎え入れたかと思えば、その舌の根も乾かぬうちに「十字架につけよ」と主イエスを追いやるエルサレムの人々。エルサレム入城から十字架へと至る主の道を囲む人々の心の動きを辿るとき、人の思いの不確かさや身勝手さを見る。ご都合主義。自分にとって益と思えば歓迎し、そうでなければ退ける。手の施しのない人の闇が、二千年の昔、エルサレムの都を覆い尽くした。この深い闇の中、主は独り十字架への道を進まれた。その深い悲しみと孤独を思う。
ところが主イエスの父なる神は、この闇により覆い消された主イエスを十字架の死から命へ、暗闇から光へと引き上げられた。十字架を経て三日目の朝のことである。父なる神は人の闇を放置されない。主イエスの十字架と復活は、人の闇が覆い尽くすかに見える世に、なおも光がもたらされる確信を与える。
2012年4月1日、棕櫚の主日からわたしの新しい奉仕が始まる。わたしは今なお闇に覆われているとしかいいようのない世に、十字架と復活の福音を語り伝えたい。キリストの体なる教会に招かれた方々と共に。そして、このわたしも世の闇を織りなす一人であることを思いつつ、わたしに向けられたものとして福音を聞きたい。これから招かれるであろう方々と共に。
キリストと共に生きることは、人の織りなす闇を突き破る神にある希望に生きることだ。それには一方で、自分の闇と向き合う作業が避けられないこととして伴う。キリストと共に生きる者は、十字架の下、自らの闇を突きつけられ、完膚なきまで打ち砕かれる。しかしもう一方で、その者は自らの闇に絶望し続けない。その者には、人の闇を打ち破られる方を信じる信仰が与えられている。
人の落とす深い闇を覗きつつ、なおも光を見る信仰、絶望のただ中で、なおも希望を見る信仰、それすなわち、主イエスの十字架と復活に示された福音に生きる信仰。この信仰を与えられ、世に遣わされる教会の使命を今ほど思うことはない。
闇を闇とも思わずやり過ごしてきた世が、今、闇を闇として突きつけられている。その中で絶望に頽れたままでいるのか、それとも希望に立ち上がるのか。その分水嶺に福音がそびえ立つ。
主イエス・キリストによって鮮やかに示された福音に繰り返し聞き、その福音を愚直なまでに語り続けることを、わたしは今神と教会の前に誓う。
松戸教会 牧師 村上恵理也
2012年3月
「ニーチェの言葉」から 自分の信仰の旅をふりかえる
若い時、ニーチェの「ツァラトゥストラはかく語りき」や「人間的な、あまりに人間的な」などの本を読んでよくわからなかった。彼は19世紀の後半に生き、20世紀の曙を前に没した(1844~1900)。24歳でスイスのバーゼル大学教授になったが、教職にあったのはわずか10年程で、その後は病気療養のため、ヨーロッパ各地を旅しながら、独特の著述と思索を続けた。
19世紀までの西欧での絶対価値と真理はキリスト教道徳だった。しかし彼は、その道徳は本物ではない、生きている人間のためではないと考えた。ニーチェに対する批判は厳しい。ナチスの思想の土台となった。ニヒリズムの哲学を語り、反ユダヤ主義者だということであるというので、20世紀の悪の哲学者ともいわれていた。はじめて、ニーチェに心をひかれたのは、すでに、私はキリスト者であり、やがて、牧師になるための神学生であって、キリスト教の只中にいて、教会・キリスト教は「これでいいのか」という疑問と、キリスト教の絶対的価値と真理は、ここにしかないという言葉に、不安と不信を感じていた。ニヒリズム、日本語で虚無主義と訳されている言葉に、ひそかな共感をしていた。自分はキリスト教信仰に生きていると思いながら、現実の教会と、そこに生きている人たちに、批判を感じていた。洗礼を受け、神学生になっていた私が、現実の教会の中で神を信じている声に、どこかウソがあると不安と不信があった。教会の中で、自分たちだけの天国を信じて喜んでいるように感じていた。私はこの世における真理、つまり、今生きている人間のための哲学・神学が必要だと思っていた。
ニーチェは牧師の子として生まれて、「神は死んだ」と語らずにおれない思いに私も共感した。よくわからないが、今を生きることの真理を求めていくのが、まこと信仰ではないか。その迷いの中で信仰の挫折をした。挫折を乗り越えるには、信じている自分を一度全部捨てるところから出発しようと決心した。「ニーチェの言葉」という“超訳”された本で、かって漠然としていたニーチェ理解を、新しく教えてくれた。
「自分を常に切り開いていく姿勢を持つことが、この人生を最高に旅することになるのだ」
「今のこの人生を、もう一度そっくりそのまま繰り返してもかまわないという生き方をしてみよ」
私にとっては、宗教は必要ない、いらないと語ることは、そこから、本物の信仰、宗教が必要となってくることだと信じている。
松戸教会 牧師 石井錦一
2012年2月
絶望名人カフカを読む
「絶望名人カフカの人生論」という本が書店にあった。なつかしくなって、つい手にとって買ってしまった。かつて「変身」という小説に感動して読んだ。つづいて「城」を読んで、自分の人間としての生き方に、どうしてよいか迷っていたときに、何となく迷っていいのだという、安心と不安を与えてくれたのが、カフカである。
フランツ・カフカは1883年7月3日にボヘミアの首都プラハ(現在のチェコの首都)で、豊かなユダヤ人の商人の息子として生まれた(同じ年に日本では志賀直哉が生まれている)。大学で法律を学び、働きながら、ドイツ語で小説を書いた。いくつかの作品を雑誌に発表し、「変身」などの単行本をだすが、生前はリルケなどのごく一部の作家にしか評価されず、無名であった。1924年6月3日41歳の誕生日の1カ月前に結核で死去した。
カフカほど絶望できる人はいない。カフカは絶望の名人だ。誰よりも落ち込み、誰よりも弱音をはき、誰よりも前に進もうとしない。しかし、だからこそ、私の若い日に、彼の言葉に率直に耳を傾けることができた。カフカは自分のことを小さな虫のように思っていたが、小説家としてのカフカは、20世紀最大の作家として、多くの人に影響を与えた人だ。日常生活の愚痴ばかり言っていたが、なぜ偉大な作家なのか。それは彼が絶望名人であったからだ。私も彼の絶望から、救われたひとりだと思っている。
カフカの人生論で、数十年たって、今、私の生活と共感する言葉を見つけた。
「カフカの食卓」
ぼくは朝昼晩の食事をとるだけで、
間食はいっさいしません。
食事の量も少なく、とくに肉類は普通の人が
少ないと感じる以上に少ないです。
おやつはぼくには害になります。
- フェリーツェへの手紙 -
カフカは基本的に菜食主義で、口にするのは、野菜、果物、ナッツ類、ミルク、ヨーグルト、ライ麦パンなどだ。宗教的な理由でなく、すべて健康のためであったが、私はもう少しぜいたくな食生活をしている。カフカの食に対する拒絶は、あきらかに彼の現実に対する拒絶、不安がもとであった。精神的にも、日常生活にも、絶望を訴えるカフカが、今生きている私には、ふしぎな安らぎと、どんなことがあっても生きていける。生きなければという思いを与えてくれる。主イエスも、十字架の絶望から復活した人だ。
松戸教会 牧師 石井錦一
2012年1月
うなだれた人生から感動、感激に生きる
正宗白鳥の「生きること」というエッセイに次のことばがある。
「キリストが十字架を背負ったのだから、信者も十字架を背負はなければならぬ。真に信者といふに値ひしてゐる信者はみんな教へに殉じてゐるのである。すべての歓楽を捨てなければならぬ。中世期に栄えてゐた修道院にはいってゐるつもりで一生を過ごさなければならぬ。昔のなんとか派の修道院は風光明媚なスイスを通る時には、道の左右に目を向けないで、うなだれて道を急いだといはれてゐる。自然の美に心をとらへられるのは堕地獄の行為とされてゐたのであった。『野の百合を見よ。ソロモンの栄華の極みの時だにもその装ひこの花の一つに及ばざりき』と、聖書において美しい言葉でうたはれてゐるが、そういう甘い言葉に惑わされて、花鳥風月を楽しもうとするのは、キリスト教の極意から離れたしわざである。永遠の生命をうけるためには幸福と感ずる現世的のすべてを捨てなければならぬのである。其の幸福は死後にあるのである」(旧かな文)
明治、大正期のキリスト者は、このように信仰をきびしくただしく守った。守ろうとした。書いた正宗白鳥自身も、やがてキリスト教を捨てた。自然を楽しみ、生きる感動も罪だという考え方が、キリスト教生活のまことのあり方だと教えられた。そのために、キリスト教信仰をもつことが、できないと思っている人がいまでもいる。キリスト教信仰は、感動と喜びをあたえるものでなければいけない。
相田みつをの「一生燃焼、一生感動、一生不悟」にそえて「感動いっぱい」のことばが心にひびく。
「人間が生きるということは、毎日何かに感動し、感激してゆくことだと私は思います。昨日は気がつかなかったものに、今日は新たな発見をして感動する。年とともにしわはできますが、心の中にしわは作りたくありません。心の中にしわができたとき、人間は感動しなくなるのでないでしょうか-感動。感激にかねはかかりません。一生悟れなくてもいいから、感動いっぱい、感激いっぱいのいのちを生きたいと思います。」
生きることに感動したい。聖書に感激したい。礼拝を喜びあふれた感動の中で守りたい。毎日の生活が、祈りの中で感激して歩みたい。今年も、出逢いの喜び、邂逅のふしぎを、私の旅路で見つけたい。キリスト教信仰はこの原点からはじまると信じている。
松戸教会 牧師 石井錦一